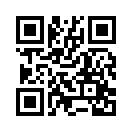新茶 牧之原に思う
いよいよ一番茶が始まる。
この時期は茶農家にとって生命線。
牧之原台地にも萌木色の茶の新芽が芽吹いている。
最近教材研究で牧之原の開拓について勉強し出した。大石貞男先生の「牧之原開拓史考」や「菊川市茶業誌」を読み漁っている。
官牧(かんまき)であった牧之原、幕末剣を鍬に持ち替え「茶畑のこやしになる」決意のもと牧之原台地に入植した中條景昭ら幕臣、大井川の川越し人足、先人の牧之原台地の開拓に思いを馳せる時、真に感極まりない。
平成の現代、昨日テレビで私の同級生の静岡大学森田教授の緑茶の安全宣言を見た。
また、防霜ファンの群立する台地を下ると途中、担い手のない放棄茶園が多くなったことにも心が痛む。最も人ごとではないが。
そして、続く茶価の低迷を考えると今の時代もまた大変な時代である。
私が生まれたころ詩人の三好達治が「牧野原茶の花十里」という詩を作っている。
三好達治は私の好きな詩人のひとりで高校時代に「あはれ花びら流れ。。。。。」と暗誦したものであった。
不勉強でこの詩は全く知らなかったのであるが、この間車から見た茶畑の中の三好達治の詩が書かれた石碑の意味がやっとわかった。ただこの「菊川市茶業誌」には「牧之原茶の花千里」となっていたが、三好達治の阿蘇草千里が混同されたのであろうか。
茶業誌を見ると友田でかつて我が家の父の祖父、私の曾おじいさん(髙栁忠吉)がお茶を揉んだ記録が出ていた。
余談ではあるが河城小学校には船乗りであった私の祖先が寄贈したワニやトカゲの剥製があった。今もあるかは不明。当時の手紙に「喜望峰からダチョウの卵を送ったが無事ついたか。」という文面がある。
小笠高校茶業科の歴史を書いた恩師の文章も拝読した。重ね重ねこの話を御本人から直にうかがえないことが惜しまれる。親孝行したいときには。。ではないが。
現在わが高にも牧之原の茶業を継ぐ若者が何人か通っている。往時の茶業科全盛時代に比べれば寂しいが。
この芽は大切に大切に育てねばと思う。。
この時期は茶農家にとって生命線。
牧之原台地にも萌木色の茶の新芽が芽吹いている。
最近教材研究で牧之原の開拓について勉強し出した。大石貞男先生の「牧之原開拓史考」や「菊川市茶業誌」を読み漁っている。
官牧(かんまき)であった牧之原、幕末剣を鍬に持ち替え「茶畑のこやしになる」決意のもと牧之原台地に入植した中條景昭ら幕臣、大井川の川越し人足、先人の牧之原台地の開拓に思いを馳せる時、真に感極まりない。
平成の現代、昨日テレビで私の同級生の静岡大学森田教授の緑茶の安全宣言を見た。
また、防霜ファンの群立する台地を下ると途中、担い手のない放棄茶園が多くなったことにも心が痛む。最も人ごとではないが。
そして、続く茶価の低迷を考えると今の時代もまた大変な時代である。
私が生まれたころ詩人の三好達治が「牧野原茶の花十里」という詩を作っている。
三好達治は私の好きな詩人のひとりで高校時代に「あはれ花びら流れ。。。。。」と暗誦したものであった。
不勉強でこの詩は全く知らなかったのであるが、この間車から見た茶畑の中の三好達治の詩が書かれた石碑の意味がやっとわかった。ただこの「菊川市茶業誌」には「牧之原茶の花千里」となっていたが、三好達治の阿蘇草千里が混同されたのであろうか。
茶業誌を見ると友田でかつて我が家の父の祖父、私の曾おじいさん(髙栁忠吉)がお茶を揉んだ記録が出ていた。
余談ではあるが河城小学校には船乗りであった私の祖先が寄贈したワニやトカゲの剥製があった。今もあるかは不明。当時の手紙に「喜望峰からダチョウの卵を送ったが無事ついたか。」という文面がある。
小笠高校茶業科の歴史を書いた恩師の文章も拝読した。重ね重ねこの話を御本人から直にうかがえないことが惜しまれる。親孝行したいときには。。ではないが。
現在わが高にも牧之原の茶業を継ぐ若者が何人か通っている。往時の茶業科全盛時代に比べれば寂しいが。
この芽は大切に大切に育てねばと思う。。
2012年04月28日 Posted by宙さん at 23:11 │Comments(2) │お茶
この記事へのコメント
牧ノ原の茶業誌は様々な形でまとめられているのですね
昔は学校に様々な物を寄贈することがあったようですね
日清戦争の清龍刀、歩兵銃、不発の流弾砲弾
なんてのも見たことがあります。
昔は学校に様々な物を寄贈することがあったようですね
日清戦争の清龍刀、歩兵銃、不発の流弾砲弾
なんてのも見たことがあります。
Posted by 久里男 at 2012年04月30日 11:22
ありがとうございました。
牧之原の茶園はは先人の汗の結晶と改めて痛感いたします。
牧之原の茶園はは先人の汗の結晶と改めて痛感いたします。
Posted by 宙 at 2012年04月30日 19:35