露無慎二先生の退官パーティー行ってきました。
5月30日に浮月楼で行われた露無慎二(つゆむ しんじ)先生(元静岡大学副学長)の退官記念パーティに参加させていただきました。学会の重鎮の方を始め総勢100人を越す皆様がお集まりになられました。私ごときが参加させて頂くのも恥ずかしいことでしたが、久しぶりに多くの静岡大学植物病理研究室の同窓の皆様方・大学の先生方ともお話ができました。後藤先生のお元気なお姿も拝見できました。滝川夫人ともお話できました。同級生の石田君舟久保君も元気そうで良かったです。(舟久保君はちょっと怖くなっていました。 )土田先輩スライドご苦労様でした。
)土田先輩スライドご苦労様でした。
滝川雄一先生の名司会(お疲れ様でございました。)
 により会も盛会の内に終わりました。露無先生のジャズ演奏も拝聴できました。
により会も盛会の内に終わりました。露無先生のジャズ演奏も拝聴できました。
露無先生・奥様おめでとうございました。
当日のパンフレット
記念品「和染 和のインテリア大橋豊久模様」いただきました。


 )土田先輩スライドご苦労様でした。
)土田先輩スライドご苦労様でした。滝川雄一先生の名司会(お疲れ様でございました。)

 により会も盛会の内に終わりました。露無先生のジャズ演奏も拝聴できました。
により会も盛会の内に終わりました。露無先生のジャズ演奏も拝聴できました。露無先生・奥様おめでとうございました。
当日のパンフレット

記念品「和染 和のインテリア大橋豊久模様」いただきました。


2010年05月31日 Posted by 宙さん at 06:47 │Comments(0)
定本濱人句集 遠州の俳人
ついに手に入れました。句集の存在を知ってから14年。やっと「定本濱人句集」をゲットしました。

平成七年に前の職場の方が持っていたこの句集をお借りしコピーさせていただきました。
その時、御礼に我が家の冬瓜をさしあげました。「冬瓜を濱人句集の礼とせり」当時作った句です。原田喬先生の佳作に入りました。平成七年に見てから実に十四年の歳月が過ぎていました。もともと発行部数が多いものではなく半ばあきらめかけていたのですが、古書店で運良く手に入れることができました。


奥付に濱人先生の「物心一如」の墨書が入った本でした。

私などが持つにはもったいない本ですが大切にしたいと思います。ただし、今月の小遣いが無くなりました。



平成七年に前の職場の方が持っていたこの句集をお借りしコピーさせていただきました。

その時、御礼に我が家の冬瓜をさしあげました。「冬瓜を濱人句集の礼とせり」当時作った句です。原田喬先生の佳作に入りました。平成七年に見てから実に十四年の歳月が過ぎていました。もともと発行部数が多いものではなく半ばあきらめかけていたのですが、古書店で運良く手に入れることができました。



奥付に濱人先生の「物心一如」の墨書が入った本でした。

私などが持つにはもったいない本ですが大切にしたいと思います。ただし、今月の小遣いが無くなりました。


2010年05月26日 Posted by 宙さん at 23:05 │Comments(0) │俳句
短冊 遠州の俳人 原田濱人(はらだ ひんじん)

夏雲は湧(わ)き諸滝(もろたき)は鳴りに鳴る
原田濱人(はらだ ひんじん)
白糸の瀧句碑・昭和三十七年一月十五日 原田八郎 号濱人と短冊の裏に鉛筆書きがあります。裏書きは、御本人の手によるものかどうかはわかりませんが。しかし、この昭和三十七年というのは奇しくも私の生まれた年です。 この短冊が手元にあるのも何かの御縁でしょうか。前にこのブログにも載せましたが私は、濱人先生(師匠のお父さんですので先生とつけましたが。)は私が俳句を教えていただいた原田喬(はらだ たかし)先生のお父様です。
この短冊が手元にあるのも何かの御縁でしょうか。前にこのブログにも載せましたが私は、濱人先生(師匠のお父さんですので先生とつけましたが。)は私が俳句を教えていただいた原田喬(はらだ たかし)先生のお父様です。

お名前はインターネットで検索していただければ沢山でてきますが。
簡単にお話させていただくと。
大正十三年「ホトトギス」第一回同人に推されます。九鬼あきゑ現椎主宰からも当時のお話をよく伺いました。虚子が、奈良で教鞭をとっていた濱人先生のお宅を尋ねて、その時四歳だった濱人先生の子喬(たかし)先生を詠んだ句が「客を喜びて柱に登る子秋の雨」です。この句は虚子の句集『五百句』にも収ねられてもいます。そして、「ホトトギス」に主観重視の論「純客観写生に低徊する勿れ」を出し、虚子と袂を分かつこととなります。原田濱人先生は地元で俳句結社「みづうみ」を興し、生涯その指導に当たられます。喬先生は跡を継がず加藤楸邨に師事し「椎」をおこすことになります。そして喬先生のお嫁さんが現在の「椎」主宰の九鬼あきゑ先生となるわけです。
簡単な説明で申し訳ございません。


ここまでで、昨日のお茶の木のならし(一番茶修了後の茶の樹の整枝)と、本業の資料作りで肩が痛いので今日はここらで終わりです。
白糸の瀧句碑・昭和三十七年一月十五日 原田八郎 号濱人と短冊の裏に鉛筆書きがあります。裏書きは、御本人の手によるものかどうかはわかりませんが。しかし、この昭和三十七年というのは奇しくも私の生まれた年です。
 この短冊が手元にあるのも何かの御縁でしょうか。前にこのブログにも載せましたが私は、濱人先生(師匠のお父さんですので先生とつけましたが。)は私が俳句を教えていただいた原田喬(はらだ たかし)先生のお父様です。
この短冊が手元にあるのも何かの御縁でしょうか。前にこのブログにも載せましたが私は、濱人先生(師匠のお父さんですので先生とつけましたが。)は私が俳句を教えていただいた原田喬(はらだ たかし)先生のお父様です。
お名前はインターネットで検索していただければ沢山でてきますが。
簡単にお話させていただくと。
大正十三年「ホトトギス」第一回同人に推されます。九鬼あきゑ現椎主宰からも当時のお話をよく伺いました。虚子が、奈良で教鞭をとっていた濱人先生のお宅を尋ねて、その時四歳だった濱人先生の子喬(たかし)先生を詠んだ句が「客を喜びて柱に登る子秋の雨」です。この句は虚子の句集『五百句』にも収ねられてもいます。そして、「ホトトギス」に主観重視の論「純客観写生に低徊する勿れ」を出し、虚子と袂を分かつこととなります。原田濱人先生は地元で俳句結社「みづうみ」を興し、生涯その指導に当たられます。喬先生は跡を継がず加藤楸邨に師事し「椎」をおこすことになります。そして喬先生のお嫁さんが現在の「椎」主宰の九鬼あきゑ先生となるわけです。
簡単な説明で申し訳ございません。



ここまでで、昨日のお茶の木のならし(一番茶修了後の茶の樹の整枝)と、本業の資料作りで肩が痛いので今日はここらで終わりです。

2010年05月23日 Posted by 宙さん at 11:35 │Comments(0) │俳句
宮柊二先生 短歌のこと
本棚を整理していたら高校時代の終寮記念にいただいたアルバムが出てきた。 もう30年も前のアルバムである。ほとんどよくもこんなものがとってあったと思える程、他愛もないゴシップが貼り付けてあるのだが。久しぶりに懐かしく見た。その中で当時有名な「なんとかコース」という雑誌に投稿した短歌の記事が目に入った。
もう30年も前のアルバムである。ほとんどよくもこんなものがとってあったと思える程、他愛もないゴシップが貼り付けてあるのだが。久しぶりに懐かしく見た。その中で当時有名な「なんとかコース」という雑誌に投稿した短歌の記事が目に入った。

フラシュで光ってしまって申し訳ございません。

宙さんの正体がまだわからないようにちょっと加工しました。(笑)

この記事のことを以前俳誌に投稿したことがあった。
以下「俳誌」に投稿した文。
「花・茶・俳句」
高柳 宙
―前略―
もともと短歌が好きで、高校時代に初めて出した歌(私は図書券位は貰えると踏んだのだが。)が宮柊二の選に入った。「青刈りの稲のあと見て何思うこの明日のなき田の悲しさよ」の歌に、「高柳君の作品は青刈り田を見て農政への不信を訴えたものだが、既念に走らず自分のペースを守った点が良い。」という評をいただいたが当時は良く分からなかった。図書券も送られてはこなかった。
後にこの歌は、私の大学の研究室では、どこでどう間違ったか、有名な文部大臣の表彰を受けた歌として、語り継がれることとなる。
その後何通か短歌の会の案内をいただいたが、高校生の自分にとっては、図書券も貰えない歌より、弓道に熱中した。運良く二段が取れた。
―中略―
ただ、本人は花(これは飯の種)も俳句も必死で取り組んでいるのだが、世間一般の人はどうも、俳句とフラワーアレンジメントをやっているというと、暇人の極地のように受け取ってくれるようである!
―中略―
親父に任せ放しの茶畑もそろそろ本腰を入れてやらねばならぬ年にもなった。
温室には、県庁の窓辺を飾るベゴニアのプランターや、沢山の春の花の苗が鉢上げを待っている。
雨天続きで灰色カビ病が心配になる。温室の棚の下の草取りもやらねば。
そろそろもう一度原点に戻って何事も考えてみる時期に来たのかもしれない。
「帰りなんいざ」
 もう30年も前のアルバムである。ほとんどよくもこんなものがとってあったと思える程、他愛もないゴシップが貼り付けてあるのだが。久しぶりに懐かしく見た。その中で当時有名な「なんとかコース」という雑誌に投稿した短歌の記事が目に入った。
もう30年も前のアルバムである。ほとんどよくもこんなものがとってあったと思える程、他愛もないゴシップが貼り付けてあるのだが。久しぶりに懐かしく見た。その中で当時有名な「なんとかコース」という雑誌に投稿した短歌の記事が目に入った。
フラシュで光ってしまって申し訳ございません。


宙さんの正体がまだわからないようにちょっと加工しました。(笑)

この記事のことを以前俳誌に投稿したことがあった。
以下「俳誌」に投稿した文。
「花・茶・俳句」
高柳 宙
―前略―
もともと短歌が好きで、高校時代に初めて出した歌(私は図書券位は貰えると踏んだのだが。)が宮柊二の選に入った。「青刈りの稲のあと見て何思うこの明日のなき田の悲しさよ」の歌に、「高柳君の作品は青刈り田を見て農政への不信を訴えたものだが、既念に走らず自分のペースを守った点が良い。」という評をいただいたが当時は良く分からなかった。図書券も送られてはこなかった。
後にこの歌は、私の大学の研究室では、どこでどう間違ったか、有名な文部大臣の表彰を受けた歌として、語り継がれることとなる。
その後何通か短歌の会の案内をいただいたが、高校生の自分にとっては、図書券も貰えない歌より、弓道に熱中した。運良く二段が取れた。
―中略―
ただ、本人は花(これは飯の種)も俳句も必死で取り組んでいるのだが、世間一般の人はどうも、俳句とフラワーアレンジメントをやっているというと、暇人の極地のように受け取ってくれるようである!
―中略―
親父に任せ放しの茶畑もそろそろ本腰を入れてやらねばならぬ年にもなった。
温室には、県庁の窓辺を飾るベゴニアのプランターや、沢山の春の花の苗が鉢上げを待っている。
雨天続きで灰色カビ病が心配になる。温室の棚の下の草取りもやらねば。
そろそろもう一度原点に戻って何事も考えてみる時期に来たのかもしれない。
「帰りなんいざ」
2010年05月20日 Posted by 宙さん at 22:15 │Comments(0) │俳句
製茶機の
今年は茶農家にとっては本当に大変な年です。我が家も連休中にお茶が刈れたのは僅か2日だけ。刈るお茶が無いという異常事態でした。 というか現在進行形。共同の製茶工場も葉が集まらず休みの日が続いています。
というか現在進行形。共同の製茶工場も葉が集まらず休みの日が続いています。
以前お世話になりました俳句結社「街」今井聖(いまい せい)主宰に選んでいただいた句です。
「街」のホームページにも載せていただいています。
製茶機の渋取り憲法記念の日 高柳 宙この作者の、季語「憲法記念日」の用い方に注目をしてほしい。何々の日というのを季語として用いるとき、大方はその日の意味を全面に押し出す。父の日、母の日然り、高名な作家の忌日然り。しかし、その日の「意味」や記念日の「意義」を述べるとほとんどは陳腐平凡な内容に終る。大方の先入観を土台に置くからである。「父の日」で父というものを描き、「母の日」で母というものを描く。啄木忌や太宰忌はそれぞれの作家の「一般的イメージ」を推し量って味付けをする。啄木や太宰に傾倒どころかろくに著書を読んでもいないくせにである。この句の「憲法記念日」は憲法についての内容とはまったく無縁である。その「日」のくる時節についてのみ焦点をあてている。五月三日の憲法記念日がくるころの茶摘から製茶への過程を詠んでいる。憲法記念日はただ五月三日であることの意味しかもたない。素朴で息の太い生活感が詠まれながら、結果として、季語というものに対する強烈なアイロニーが知的に表現されている。(2008.04.28)
 というか現在進行形。共同の製茶工場も葉が集まらず休みの日が続いています。
というか現在進行形。共同の製茶工場も葉が集まらず休みの日が続いています。
以前お世話になりました俳句結社「街」今井聖(いまい せい)主宰に選んでいただいた句です。
「街」のホームページにも載せていただいています。
製茶機の渋取り憲法記念の日 高柳 宙この作者の、季語「憲法記念日」の用い方に注目をしてほしい。何々の日というのを季語として用いるとき、大方はその日の意味を全面に押し出す。父の日、母の日然り、高名な作家の忌日然り。しかし、その日の「意味」や記念日の「意義」を述べるとほとんどは陳腐平凡な内容に終る。大方の先入観を土台に置くからである。「父の日」で父というものを描き、「母の日」で母というものを描く。啄木忌や太宰忌はそれぞれの作家の「一般的イメージ」を推し量って味付けをする。啄木や太宰に傾倒どころかろくに著書を読んでもいないくせにである。この句の「憲法記念日」は憲法についての内容とはまったく無縁である。その「日」のくる時節についてのみ焦点をあてている。五月三日の憲法記念日がくるころの茶摘から製茶への過程を詠んでいる。憲法記念日はただ五月三日であることの意味しかもたない。素朴で息の太い生活感が詠まれながら、結果として、季語というものに対する強烈なアイロニーが知的に表現されている。(2008.04.28)
2010年05月11日 Posted by 宙さん at 22:58 │Comments(0) │俳句
浦岡敬一先生のこと
我が家の玄関に額装した墨書が何枚か掛けてあります。その中で最も大切にしているものがこの書です。

日本映画の編集者として活躍された浦岡敬一先生からいただいた墨書です。胡蝶蘭の絵に文章を入れていただいた貴重な書です。



浦岡敬一(うらおか・けいいち)山田洋次、大島渚、寺山修司、深作欣ニなど・・・
日本映画の巨匠たちと格闘した映画編集者の全仕事に迫る
1930年生まれ
1948年、松竹に入社。浜村義康に付き、小津安二郎監督作品などの編集助手を務め、1958年「人間の条件」(監督:小林正樹)で一本立ち。「馬鹿が戦車でやって来る」(監督:山田洋次)、「青春残酷物語」(監督:大島渚)、「黒蜥蝪」(監督:深作欣ニ)などを手掛ける。1969年、松竹を退社後、「愛のコリーダ」(監督:大島渚)、「復讐するは我にあり」(監督:今村昌平)、「ウルトラマン」(監督:実相寺昭雄)など、幅広い作品を担当する。1983年「東京裁判」(監督:小林正樹)で芸術選奨文部大臣賞受賞。1989年、「帝都物語」(監督:実相寺昭雄)、「優駿 ORACIO’N」(監督:杉田成道)で日本アカデミー賞優秀編集賞受賞。この間、日本映画編集協会の設立に尽力し、初代編集協会理事長を務めた。
出典マスターズ・オブ・カット Vol.1 日本映画を斬った男 映画編集者・浦岡敬一の世界
この書は、奥様の浦岡ユキ様が私と一緒に俳句をやっていた関係で、主宰のお宅に御夫婦でお見えになった時に「胡蝶蘭」の鉢植えを差し上げた御礼としていただいたものです。
病後のことでもあり、こんな書き付けも一緒に入っておりました。

先生は俳誌「椎」の「ああ人生モンタージュ」の中で撮影所時代のお話や、映画のお話を連載されました。映画のことなど何もわからない私も先生のお話は毎回楽しみにしておりました。
懇親会で司会をさせていただいたとき車椅子で奥様と御来場いただき、貴重なお話を伺いました。しかし、緊張のあまり私はなんと先生のお話の途中で「ありがとうございました。」と言ってしまったのでした。 今思えば本当に失礼なことでした。
今思えば本当に失礼なことでした。


日本映画の編集者として活躍された浦岡敬一先生からいただいた墨書です。胡蝶蘭の絵に文章を入れていただいた貴重な書です。



浦岡敬一(うらおか・けいいち)山田洋次、大島渚、寺山修司、深作欣ニなど・・・
日本映画の巨匠たちと格闘した映画編集者の全仕事に迫る
1930年生まれ
1948年、松竹に入社。浜村義康に付き、小津安二郎監督作品などの編集助手を務め、1958年「人間の条件」(監督:小林正樹)で一本立ち。「馬鹿が戦車でやって来る」(監督:山田洋次)、「青春残酷物語」(監督:大島渚)、「黒蜥蝪」(監督:深作欣ニ)などを手掛ける。1969年、松竹を退社後、「愛のコリーダ」(監督:大島渚)、「復讐するは我にあり」(監督:今村昌平)、「ウルトラマン」(監督:実相寺昭雄)など、幅広い作品を担当する。1983年「東京裁判」(監督:小林正樹)で芸術選奨文部大臣賞受賞。1989年、「帝都物語」(監督:実相寺昭雄)、「優駿 ORACIO’N」(監督:杉田成道)で日本アカデミー賞優秀編集賞受賞。この間、日本映画編集協会の設立に尽力し、初代編集協会理事長を務めた。
出典マスターズ・オブ・カット Vol.1 日本映画を斬った男 映画編集者・浦岡敬一の世界
この書は、奥様の浦岡ユキ様が私と一緒に俳句をやっていた関係で、主宰のお宅に御夫婦でお見えになった時に「胡蝶蘭」の鉢植えを差し上げた御礼としていただいたものです。
病後のことでもあり、こんな書き付けも一緒に入っておりました。

先生は俳誌「椎」の「ああ人生モンタージュ」の中で撮影所時代のお話や、映画のお話を連載されました。映画のことなど何もわからない私も先生のお話は毎回楽しみにしておりました。
懇親会で司会をさせていただいたとき車椅子で奥様と御来場いただき、貴重なお話を伺いました。しかし、緊張のあまり私はなんと先生のお話の途中で「ありがとうございました。」と言ってしまったのでした。
 今思えば本当に失礼なことでした。
今思えば本当に失礼なことでした。
2010年05月04日 Posted by 宙さん at 17:12 │Comments(0) │映画
手鑑その1 豊臣秀次
少し手前味噌になりますが、集めた短冊や書を紹介します。なお当方素人につき真贋の保証はできません。ノークレームノーリターンで・・・ついついオークションのノリになってしまいました。 僅かな小遣いの中から妻や子供はたまた職場の皆様から例の如く冷ややかな目でみられながらもこつこつと集めたものです。
僅かな小遣いの中から妻や子供はたまた職場の皆様から例の如く冷ややかな目でみられながらもこつこつと集めたものです。 (御本人からいただいた短冊は勿論本物ですが。)第1弾は手鑑(てかがみ)です。
(御本人からいただいた短冊は勿論本物ですが。)第1弾は手鑑(てかがみ)です。
手鑑(てかがみ)とは、厚手の紙で作られた折帖に、古筆の断簡を貼り込んだ作品集。古筆を手軽に鑑賞できるところからこの名で呼ぶが、その形状から、鏡を開くことへの見立ても含んでいるかもしれない。「手鏡」とも。桃山時代以降、茶の湯の流行にしたがって、古筆が鑑賞の対象として愛好されるようになると、経巻や歌書・消息などの巻子本や冊子装からその一部を切り取って「古筆切」として収集することが流行した。手鑑は、こうした切を台帳に編集したものである。古筆愛好家たちは、数多くの古筆・名筆を鑑賞するために、古筆切を帳面に貼り込んで手鑑を作成した。武家や公家においては、手鑑は大切な嫁入り道具ともなったという。また、古筆家、古筆見、あるいは単に古筆と呼ばれた古筆鑑定の専門家(古筆了佐など)は、鑑定の標準とすべき代表的な古筆切を法帖に押した手鑑を携行し、鑑定の基準とした。「翰墨城」「藻塩草」「見ぬ世の友」「大手鏡」などは国宝。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
表紙の角は「十大紋」の一つの「沢瀉(おもだか)」の家紋と思われる家紋が銀で掘られ装丁されています。由緒正しい物かもしれません。


五大紋(ごだいもん)は、日本の家紋のうち、一般的に特に多く分布する藤、桐、鷹の羽、木瓜、片喰の5つの紋のことを指す。これらを、いつごろに誰が何を基準にして定めたものかは不詳である。またこれらに、蔦、茗荷、沢瀉、橘、柏の5つを加えて「十大紋」と呼ぶ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
調べてみると福島沢瀉と呼ばれる家紋に似ています。詳細は定かではありません。
箱はあるのですがあまりにも傷みが激しいため、職場の方に私の桐の衣装箱を改良(笑)して作っていただきました。立派な箱ができ真に職人技と感激しています。さらに職場の書家に「古筆手鑑」と箱書きをしていただきました。感謝です。

立派な入れ物も完成。
中身については随時御紹介いたします。ちょっとだけ紹介。

豊臣関白秀次公・西行法師・弘法大師・一休和尚 いずれも極札付き
なおこのページへの入札は無効です。
 僅かな小遣いの中から妻や子供はたまた職場の皆様から例の如く冷ややかな目でみられながらもこつこつと集めたものです。
僅かな小遣いの中から妻や子供はたまた職場の皆様から例の如く冷ややかな目でみられながらもこつこつと集めたものです。 (御本人からいただいた短冊は勿論本物ですが。)第1弾は手鑑(てかがみ)です。
(御本人からいただいた短冊は勿論本物ですが。)第1弾は手鑑(てかがみ)です。手鑑(てかがみ)とは、厚手の紙で作られた折帖に、古筆の断簡を貼り込んだ作品集。古筆を手軽に鑑賞できるところからこの名で呼ぶが、その形状から、鏡を開くことへの見立ても含んでいるかもしれない。「手鏡」とも。桃山時代以降、茶の湯の流行にしたがって、古筆が鑑賞の対象として愛好されるようになると、経巻や歌書・消息などの巻子本や冊子装からその一部を切り取って「古筆切」として収集することが流行した。手鑑は、こうした切を台帳に編集したものである。古筆愛好家たちは、数多くの古筆・名筆を鑑賞するために、古筆切を帳面に貼り込んで手鑑を作成した。武家や公家においては、手鑑は大切な嫁入り道具ともなったという。また、古筆家、古筆見、あるいは単に古筆と呼ばれた古筆鑑定の専門家(古筆了佐など)は、鑑定の標準とすべき代表的な古筆切を法帖に押した手鑑を携行し、鑑定の基準とした。「翰墨城」「藻塩草」「見ぬ世の友」「大手鏡」などは国宝。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
表紙の角は「十大紋」の一つの「沢瀉(おもだか)」の家紋と思われる家紋が銀で掘られ装丁されています。由緒正しい物かもしれません。


五大紋(ごだいもん)は、日本の家紋のうち、一般的に特に多く分布する藤、桐、鷹の羽、木瓜、片喰の5つの紋のことを指す。これらを、いつごろに誰が何を基準にして定めたものかは不詳である。またこれらに、蔦、茗荷、沢瀉、橘、柏の5つを加えて「十大紋」と呼ぶ。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
調べてみると福島沢瀉と呼ばれる家紋に似ています。詳細は定かではありません。
箱はあるのですがあまりにも傷みが激しいため、職場の方に私の桐の衣装箱を改良(笑)して作っていただきました。立派な箱ができ真に職人技と感激しています。さらに職場の書家に「古筆手鑑」と箱書きをしていただきました。感謝です。


立派な入れ物も完成。
中身については随時御紹介いたします。ちょっとだけ紹介。

豊臣関白秀次公・西行法師・弘法大師・一休和尚 いずれも極札付き
なおこのページへの入札は無効です。

2010年05月01日 Posted by 宙さん at 09:18 │Comments(0) │書
カテゴリ
花束 (4)
花 (69)
カタクリコ (1)
ガーデニング (4)
お茶 (29)
書 (4)
歴史 (4)
映画 (1)
俳句 (23)
お菓子 (4)
伝統・文化 (24)
牧野アナ (7)
アレンジメント (8)
短冊 (7)
食 (12)
自然 (12)
びっくり (62)
お酒 (9)
アウトドア (2)
健康 (36)
漫画 (1)
二十四節気 (1)
弓 (36)
農業 (25)
剣道 (1)
生涯教育 (3)
百周年 (16)
ゲーム (2)
恩師 (4)
学校 (25)
笑 (24)
村 (1)
村 (0)
旅 (1)
旅 (0)
文化 (7)
お土産 (0)
感謝 (1)
最近の記事
過去記事
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
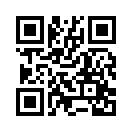
アクセスカウンタ
読者登録
プロフィール
宙さん
